
神奈川県丹沢山地の丹沢表尾根(おもておね)を歩いてきました。
表丹沢の主峰、塔ノ岳より南東へと伸びる尾根です。相模平野を一望できる非常に展望の良い尾根道であり、丹沢エリアの中でも特に高い人気を誇るルートです。
お気に入りの山のお気に入りのルートをのんびりと歩いてきました。
2017年10月1日に旅す。
いつの間にか夏の香りはすっかり遠退き、秋の気配が濃厚に漂う季節になってまいりました。

こんにちは。週末が近づくとソワソワと落ち着きの無くなる、重篤な好山病患者のオオツキです。
10月頭と言うのは、夏山シーズンは完全に終わりつつも紅葉にはまだ早いという、いささか中途半端な季節であります。こんな時は、気合の入った遠征登山ではなく、近場のお気に入りの山を適当にふらつくに限ります。
天気も良さげな休みの日。特に予定も決まっていないけど、とりあえず山にでも行こうかな。そんな気分になったとき、ふらっと赴く馴染みの山域。すなわちホームグラウンドの山です。
お気に入りの山であれば何処だって良いのですけれど、概ね以下の条件を満たしているような山がホームグランドに適しているかと思います。
1.自宅からのアクセスが良好な場所であること
思い立ったときすぐに行ける場所である事が理想です。そうなると、やはり自宅からある程度近い場所であることが望ましいですね。
2.複数のコースをもつ、ある程度懐の深い山であること
どんなに良い山であっても、同じコースばかり何度も歩いていたら、いつかは飽きてしまいます。行くたびに色々なコース取りが出来るような、複数のコース・登山口を持つ山であることが望ましいです。
都内在住の人にとって、この条件を満たしている山として真っ先に思い浮かぶのは、やはりここでしょうかね。

関東一安い運賃が自慢[要出典]の京王線一本でアクセス可能です。裏高尾エリアまで含めれば、実に多種多彩なコース取りが可能であり、何気に懐の深い山でもあります。
欠点と言えば、人が多すぎることでしょうか。あとは、やはりイージーすぎると言うのもあるかもしれません。もう少し骨のある登山がしたいと願う人からすれば、やや不満の残るところです。
そんな訳で、私がホームグラウンドとして足繁く通っているのは、表丹沢と呼ばれる一帯です。

小田急線と神奈中バスの組み合わせでアクセスできます。運行本数が多く、運賃も安めでアクセスに関しては文句なしです。問題はと言えば、どの山もあまり手軽とは言えない点でしょうか。
海の近くからせり上がっている丹沢山塊は、何れの山も登山口から山頂までの標高差が大きめです。登り応えを求める人には無問題でしょうが、手軽さと言う点おいてはやや難ありです。
私の場合、最低でも5時間以上は歩かないと歩いた気分になれない性質なので、手軽でないことは特に欠点とはなりません。
そんな訳で、本日は表丹沢エリアの中でも特にお気に入りの、表尾根コースを歩きます。
コース

ヤビツ峠から表尾根コースを歩き、表丹沢の主峰、塔ノ岳へ登頂。
下山はバス本数の多い大倉へ下ります。これと言って特筆すべき点の無い、極めてオーソドックスなルートです。

1.丹沢表尾根 アプローチ編 表尾根の入り口、ヤビツ峠へ
7時18分 新百合ヶ丘駅
小田原行きの急行電車に乗り込み、秦野駅(はだのえき)へ向かいます。

本日はそんなに気合の入った山行きではないため、比較的ゆっくりとした始動です。
8時14分 秦野駅に到着しました。安全確認のためと称した微妙な遅延が発生する、何時もの小田原急行クォリティが遺憾なく発揮されております。

8時18分発のヤビツ峠行きのバスに乗ろうとしましたが・・・満員でした。すぐに臨時便が増発されて、なんとかそれに乗れました。この対応の柔軟さは、流石は天下の神奈中バスです。

9時10分 ヤビツ峠に到着しました。途中の道すれ違いが多発し、大分時間がかかっての到着です。この時間にもう下ってくる人と言うのは、一体何時頃から行動を開始しているのでしょうか??

2.表尾根最初のピーク、三ノ塔を目指す
軽く腹ごしらえをしたり、15分ほど準備に費やして、9時25分に登山を開始します。最初からしばしの間は舗装道路歩きです。

薄っすらと紅葉が色付き始めていました。見ごろを迎えるのはまだまだ先のことです。

9時50分 富士見橋に到着しました。ここまではずっと緩やかな下り道です。せっかく(バスが)稼いだ位置エネルギーが無駄に費やされてしまった。

最近トレランを始めたと言う本日の同行者HI君に、歩き始めて早々に置いていかれる。

登り始めからしばらくは、ありふれた樹林帯の道です。展望が開けるまではしばしの我慢です。

足元にホトトギスの花が咲いていました。ユリ科に属する多年草です。

丹沢名物階段地獄が始まり、あっという間にトレイルランナーに置いて行かれる。

私の歩行スタイルは基本的にカメ型です。歩行速度自体は速くありませが、あまり休まずに黙々と歩き続けるので、結果として標準コースタイムよりは少しだけ速くなります。
HI君は小まめに休憩しつつ飛ばすウサギ型であるようです。
背の高い木が無くなり、視界が開けてきました。森林限界を越えるような標高でもないのに、この辺りに背の高い木が無いのは、酸性雨の影響だと言われています。


背後にはヤビツ峠を挟んで向かいの大山(1,252m)が見えます。均整の取れたとてもイイ形をした山ですね。


眼下には神奈川県々歌にも歌われた相模の沃野が広がります。「光あらたに」じゃなくて古い方のやつね。

薄っすらと霞んでしまってはいますが、辛うじて江ノ島も見えました。

いつの間にか、空がどんよりと曇ってきてしまっておりますな。海に近い表丹沢エリアは、湿った空気が流入しやすいためか、なかなかスカッと快晴にはなってくれません。
10時40分 二ノ塔に登頂しました。表尾根コースにおける最初のチックポイントですが、ここはあまり展望がよろしくありません。素通りして次の三ノ塔へ向かいます。

二ノ塔から三ノ塔まで10分ちょっとの道のりです。三ノ塔の方が全然眺めが良いので、ここはもうひと頑張りすることを強く推奨します。

三ノ塔に向かって登り返します。軽快に颯爽と階段を駆け上がるウサギと、息を切らしながら必死に登るカメ。


10時50分 三ノ塔に登頂しました。ここからがいよいよ表尾根の真骨頂です。一気に展望が開けます。

目の前には富士山。10月初旬ではまだ降雪は始まらないと見えて、雪のまったく無い夏富士の姿をしています。

これから歩く表尾根の稜線と、その先にあるゴール地点の塔ノ岳もバッチリと見えます。

三ノ塔は、傍目から見ると見事なまでの台形をした山で、山頂部は平坦な大地状となっています。

次のチェックポイントである鳥尾山が、はるか眼下に見えます。表尾根はここで一旦大きく高度を落とします。

3.好展望の稜線歩きが続く表尾根の登山道
と言うことで、お地蔵さんに見送られながら、鞍部に向かって降下を開始します。

始めの内は階段が整備されています。ここはまだ歩きやすいです。

高度感バツグンのガレ場を下ります。山と高原地図に危険アイコンと「急坂」という記述のある場所です。

あんなに下に見えていた鳥尾山が、あっという間に同高度になりました。

無理矢理木の根をまたぐ様に付けられていた道に、いつの間にか真新しい木段が整備されていました。

一年前はこんな状態でした。人気のコースと言うだけあって、こうして常に改良が加えられているのですね。

気持ちのいい稜線歩きが続きます。割とアップダウンの激しいコースですが、眺めが良いためあまり苦には感じられません。

11時30分 鳥尾山に到着しました。まるで豪雪地帯にある建物のようなデザインの小屋が立っています。

振り返ってみる三ノ塔。山頂が平たい山であることが大変良くわかりますな。

先ほどのガレ場を下る登山者の姿が見えました。端から見ると、殆ど崖みたいなところを下っていますね。

ここからはしばらく、最高の稜線ハイクを楽しめます。都心近郊でこれだけの展望を味わえる場所は、他にはなかなか無いのではないでしょうか。


11時50分 行者ヶ岳を通過します。その名が示すとおり、いかにも修験者が好みそうな岩々しいピークです。

このピークの存在が、表尾根コースに適度な緊張感を与えてくれており、このルートの魅了を高めることに一役買っています。
絶景に見惚れるトレイルランナー。単にウサギがカメの到着を待っているだけとも言う。

行者ヶ岳には鎖場が2箇所存在しますが、塔ノ岳方向に向かう場合はどちらも下りになります。これは1つ目の鎖です。別に鎖がなくても通行可能な鎖いらない場です。

こちらは一つ目よりもずっと高さがあり、割と本格的な鎖場です。

下から見るとこんな感じです。足を乗せるステップは沢山あるので、あせらず慎重に降りればなんら危険なことはありません。

ガレ場を登り返します。相変わらずハイペースのトレイルランナーにどんどん引き離されていく。

この光景だけを見ると、あたかも3,000メートル峰の稜線を歩いているかのように見えますね。

振り返って望む行者ヶ岳。反対向きに歩くのもなかなかか楽しそうですね。三ノ塔への登り返しで涙目になりそうではありますが。

この登りが何気にキツイ。ちょうど疲労が溜まって来るタイミングなのか、新大日の登りはキツイというイメージがすっかり定着しています。

12時30分 新大日に到着しました。空腹を覚える時間になってきた頃合だったので、ここで昼食をとりつつ休憩を取りました。

4.丹沢表尾根 登頂編 無情にもガスに覆われてしまった塔ノ岳
いかにも丹沢らしい木道が続きます。この辺りは比較的アップダウンも少なく、ここまでの疲労が溜まってきている体に優しい道です。

ここでまさかのガス襲来。山頂は雲に覆われてしまいました。なんってこったい。塔ノ岳は展望が売りの山なのに・・・

新大日でメシを食っている場合ではなかったのですね。一面真っ白の残念な光景の中を最後の登りです。

13時25分 塔ノ岳に登頂しました。嗚呼無情なるかな、遅かりし由良之助であります。やはり展望にありつくには、午前中に到着できないと駄目ですね。

カメラを向けられたらとりあえずヘン顔アピールするのが、彼の流儀らしい。

山頂はガッスガスで、遠望は全く利きません。辛うじて眼下のユーシン渓谷の姿がチラ見えしました。

この光景だけではあんまりなので、晴れている日の参考画像を置いておきますね。
<参考画像>

5.下山はバス本数が多い大倉へ
何も見えないし、寒くなってきたので僅かな山頂滞在時間で下山を開始します。下山ルートは何時ものバカ尾根です。

ガレ場の下り。晴れていれば前方に相模湾を一望できます。晴れていればね。

丹沢名物階段地獄が延々と続きます。何度歩いても膝ブレイカーな道です。

ガスっているのは頂上部だけらしく、下るにつれて雲から出ました。

突然走り始めたトレイルランナーに、またしても置いて行かれる。

14時45分 堀山の家に到着。ここからは先は一時的に道の傾斜が緩んで、ほっと一息つけます。

15時20分 見晴茶屋を通過します。ここのウッドデッキは土足禁止です。目立たないところに書いてあるので、気付かずに乗っかる人多数でしたが。

下山を続行します。謎のアピールをするトレイランナーを先頭に、どんどん下っていきます。

15時45分 観音茶屋に到着しました。周囲が大分暗くなってきました。秋分の日を過ぎると、急激に日が短くなっていきますね。

体が糖分を欲していたので、ここで小休止して観音茶屋名物の牛乳プリン(150円)を頂きます。大倉尾根を利用の際には、必ず押さえておくべきマストな一品です。

観音茶屋を過ぎれば、大倉まではもう一息です。日が完全に落ちる前に足早に下ります。

舗装道路出てからもバカ尾根はまだ終わりません。バス停までは一道あります。


16時30分 大倉バス停に到着しました。行動開始からちょうど7時間でゴールです。程よいボリューム感の山行きでありました。

大倉へ下る最大の利点は、バスの運行本数が多いことです。さほどの待ち時間も無く、スムーズに帰還です。

冒頭で「今回はサラっと簡単に流す」とか言っておきながら、結局ダラダラと冗長な記事になってしまいました。短く簡潔に記事をまとめるのって、意外と難しいのだと思わされた次第であります。
通算すれば過去に10回以上は歩いているであろう表尾根コースですが、やはりこの道は何度歩いても楽しいです。
歩行距離は少々長めですが、ひたすら登り続ける大倉尾根とは違って、程よくアップダウンを繰り返す変化に富んだ道は飽きることがありません。
行き先に迷ったら、とりあえずここに行けば良い思いが出来ると言う、実に安心感のある鉄板コースと言えるでしょう。
<コースタイム>
ヤビツ峠(9:25)-富士見橋(9:50)-二ノ塔(10:40)-三ノ塔(10:50)-鳥尾山(11:30)-行者ヶ岳(11:50)-新大日(12:30~12:55)-塔ノ岳(13:25~13:45)-花立山荘(14:05)-堀山の家(14:45)-見晴茶屋(15:20)-観音茶屋(15:45~16:10)-大倉BS(16:30)
完
最後までお読みいただき、ありがとうございました。













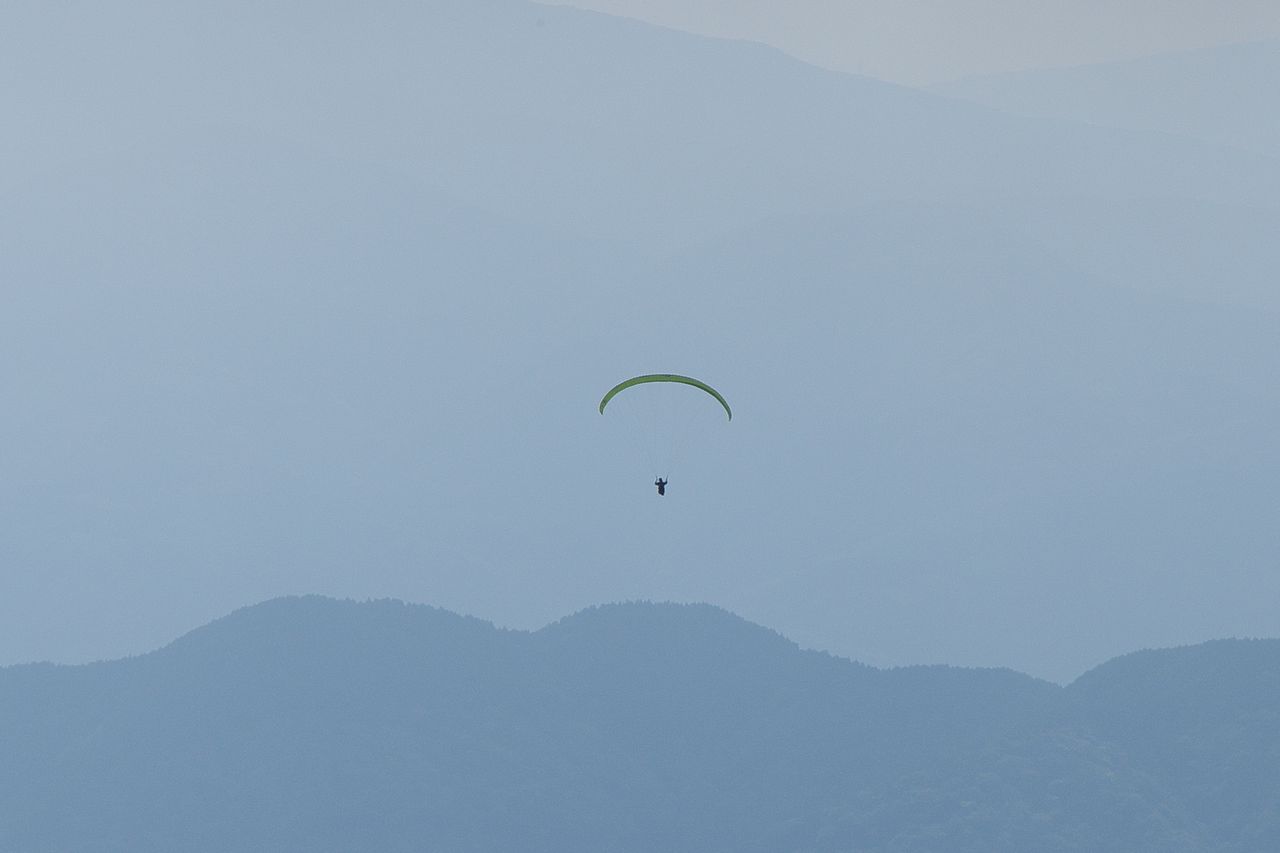









コメント